生理痛とPMSの違い、根本原因である女性ホルモンと自律神経の関係性とは?
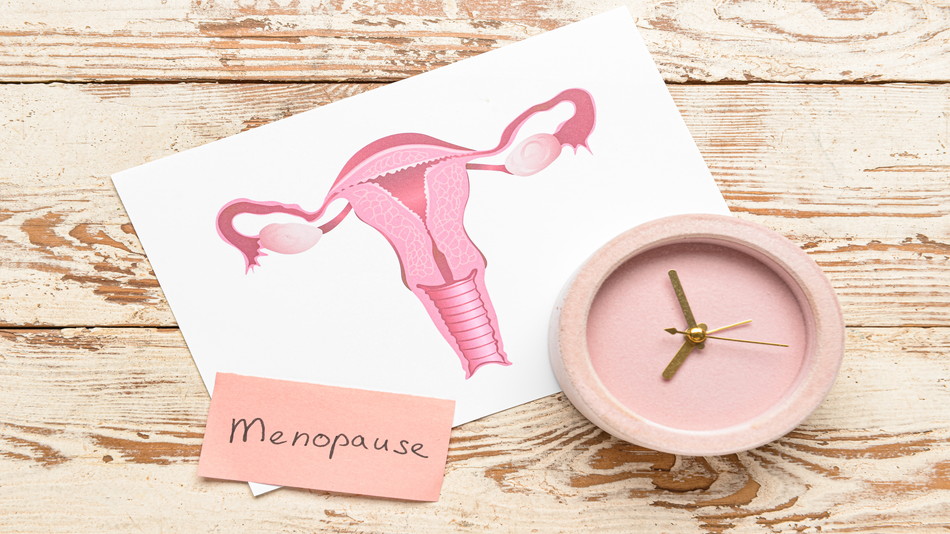
「生理前になるとイライラする…」「お腹や腰が痛くてつらい…」生理にまつわる不調は人それぞれですが、よく混同されるのが PMS(月経前症候群) と生理痛です。
この2つは似ているようで発生のタイミングや原因が異なります。正しく理解することで、自分の症状に合ったケアができるようになります。
今回のコラムでは生理痛とPMS(月経前症候群)の違い、女性ホルモンと自律神経の関係性についてお伝えしていきます。
生理痛とPMSの違いとは?
PMS(月経前症候群)とは?
PMSは、生理が始まる3日~10日前に現れる心身の不調を指します。生理が始まると自然に症状が和らぐのが特徴です。
PMSの主な症状には、イライラや不安、抑うつなどの精神的な不調のほか、頭痛やめまい、むくみや体重増加、乳房の張りや痛み、倦怠感や集中力の低下などがあります。
主な原因としては、自律神経の乱れによる女性ホルモンの急激な変動が挙げられます。排卵後に増えるプロゲステロン(黄体ホルモン)が自律神経に影響を与えることで、精神的・身体的な不調を引き起こします。また、ストレスや生活習慣の影響で交感神経と副交感神経のバランスが崩れると、PMSの症状が悪化することがあります。
生理痛とは?
生理痛は、生理が始まってから数日間にかけて感じる下腹部の痛みや腰痛などを指します。
生理痛の主な症状には、下腹部の鈍痛や激痛、腰痛、だるさ、吐き気や下痢、頭痛やめまいなどがあります。
生理痛の主な原因としては、プロスタグランジンの過剰分泌が挙げられます。プロスタグランジンは子宮を収縮させる物質であり、分泌量が多いと痛みが強くなります。また、体の冷えや血行不良によって子宮の筋肉が硬くなり、痛みを感じやすくなることがあります。
女性ホルモンと自律神経の関係
女性ホルモン(エストロゲン・プロゲステロン)は、自律神経と密接に関わっています。
PMSと生理痛は異なるメカニズムで起こりますが、どちらも女性ホルモンの変動と自律神経の働きに大きく影響されています。そして、女性ホルモンバランスは自律神経の働きによって左右されます。
PMSは生理前に起こる心身の不調でありイライラやむくみなどが特徴です。一方、生理痛は生理中の痛みであり下腹部痛や腰痛が主な症状となります。PMSや生理痛の症状が強くなるもの、根本には自律神経の乱れが女性ホルモンの変動に影響を与えるためです。
カイロプラクティックでは、自律神経が乱れる根本原因である背骨や骨盤での神経圧迫を取り除き、自律神経の働きを正常化することで、生理痛やPMSの改善をサポートします。
生理に関する不調を軽減するには自律神経を整え、ホルモンバランスをサポートすることが重要です。カイロプラクティックケアを取り入れながら、日々の生活で自分の体と対話しながら快適な毎日を目指していきましょう!

執筆者中島 恵
新潟県東蒲原郡出身。柔道整復師資格取得後、2007年から2018年まで柔道整復師として接骨院勤務。その後、勤務地を横浜に変え整骨院で勤務。
シオカワスクールの哲学教室で塩川雅士D.C.からカイロプラクティックの自然哲学を学んだことや、塩川カイロプラクティック治療室で実際の臨床現場を見学させていただいたことで、哲学・科学・芸術の重要性を知る。
現在は、前田カイロプラクティック藤沢院での診療を通じて地域社会の健康に寄与しながら、シオカワスクールでは女性初のインストラクターとして後任の育成にも力を入れている。
自分自身が女性特有の悩みで悩んでいた経験を活かし、誰にも相談できずにどこへ行っても改善されずに悩んでいる女性に寄り添えるようなカイロプラクターを目指している。



